[AI時代に多様化・分散化するデータセンター新時代]
本書の概要
急速に普及し始めた生成AI(人工知能)は、今後、日本に多大な経済効果をもたらすと予測される一方で、膨大なデータ処理に必要な電力需要や通信トラフィックの増大などの問題も急浮上しています。
また、AIの利用拡大や通信トラフィックの増大によってデータセンターへの需要も急増しており、その整備は日本においても重要な政策課題となっています。
経済産業省および総務省は、今後のデータセンターの整備を見据えて、電力(ワット)と通信(ビット)の効果的な連携(ワット・ビット連携)に向けた、「ワット・ビット連携官民懇談会」を2025年3月に発足し、同年6月に「ワット・ビット連携官民懇談会取りまとめ1.0」を公表しました。
一方、気候変動問題の解決に向けて、日本の「第7次エネルギー基本計画」(2025年2月に閣議決定)においては、2040年度の再エネ比率40〜50%という、大幅な再エネの主力電源化の目標も設定されました。
このような背景を踏まえ、本書では、電力・通信業界の第一線で活躍されている専門家の方々による日本初の「ワット・ビット連携データセンター」の報告書です。
AI時代のデータセンターを実現するために、脱炭素化の加速とともにどのように電力・通信インフラ整備を進めていくのか。AI時代に多様化・分散化するデータセンターについて読み解いていきます。
本書のポイント
- ワット・ビット連携の本質が理解できる
- AIデータセンターの現状が整理できる
- ワット・ビット連携が生み出す新たなデータセンター産業が見える
- 電力需給の調整弁となるAIデータセンターの位置づけが理解できる
- 未来のデータセンター構築手法が見える
発売中

(本体100,000円+税10%)
CD(PDF)版:99,000円
(本体90,000円+税10%)
電子版:99,000円
(本体90,000円+税10%)
目次
1.1 なぜ今、ワット・ビット連携なのか
1.1.1 情報側の主導ではなく、電力側の事情にも合わせる
1.1.2 情報と電力のシステムを新しい姿に変えていく
1.1.3 モノからデジタルへ、インフラの再定義
1.2 「ワット」「ビット」「データセンター」の現状整理
1.2.1 データセンター新設に伴う電力需要が爆発的に増加
1.2.2 「時間のずれ」と「立地のずれ」
1.2.3 通信トラフィックがクラウドに集中
1.2.4 ダークファイバの利用がデータセンターを局所化
1.3 脱炭素化とAIで未来はどう変わるか
1.3.1 データセンターが電力需給の調整弁となる
1.3.2 分散と調整の「日本版ネオクラウド」へ
1.3.3 データと計算資源の分離
1.3.4 経済安全保障の見地からも脱炭素は必須
1.4 全光ネットワークが果たす役割
1.5 課題克服に向けた方策とは
1.5.1 「ベースロード電源」の導入
1.5.2 半導体価格低下や計算効率改善でデータセンター経営が変わる
1.5.3 「GPUライセンス制」導入の可能性
1.5.4 「電気を貯める」ことに関する新たな視点
1.6 ワット・ビット連携がもたらすインパクト
1.6.1 新たな産業の生態系が生まれる
1.6.2 日本が世界をリードする日も
1.6.3 「デジタルガバナンス」が日本の新たな強みになる
1.7 ワット・ビット連携を実現するためのポイント
1.7.1 3つのステップで進行中
1.7.2 「Proof of Business」(事業実証)の追究
1.7.3 これから重要となる3つのポイント
〔1〕 「As-Is」(現状通り)と「To-Be」(あるべき姿)の視点
〔2〕 「More from Less」の発想
〔3〕 分散化
1.7.4 整いつつある「民主導・官支援」の環境
1.7.5 原点に立ち返ることで、新たな視座が開ける
1.8 EVやパソコン、揚水発電とワット・ビット連携の関連は
1.8.1 分散エネルギーとしてのEVのポテンシャル
1.8.2 EVの新しい存在意義
2.1 高まるデータセンターの価値
2.1.1 エネルギー産業における位置づけ
2.1.2 政策とワット・ビット連携
2.1.3 ワット・ビット連携官民懇談会
〔1〕 電力・通信・データセンターによる新生態系の創出
〔2〕 国際展開を念頭に
2.1.4 2025年6月:「取りまとめ1.0」を発表
〔1〕 短期テーマ:足元のデータセンター需要への対応
〔2〕 中期テーマ:新たなデータセンター集積拠点の実現
〔3〕 長期テーマ:データセンター地方分散・高度化の推進
〔4〕 補足:重要なフィジカルAI・再エネ化/省エネ化・国際的な視点
2.2 データセンター最前線
2.2.1 AIとデータセンター
〔1〕 調整余地を持つ電力需要
〔2〕 近くで推論、遠くで学習
〔3〕 AI-RANの可能性
2.2.2 ワット・ビット連携に向けた新たな視点
〔1〕 ワット・ビット+「モレキュラー」
〔2〕 連携のための考え方
2.2.3 中国のエネルギー・通信のインフラ戦略
〔1〕 内陸で発電、都市部へ送電
〔2〕 超高圧直流送電の導入
〔3〕 データセンターは「東数西算(とうすうせいさん)」
〔4〕 東数西算の実際
〔5〕 日本での展開
2.2.4 データセンターとクラウドシステムの現状
〔1〕 AIによる変化
〔2〕 「ワット・ビット+シェル連携」
〔3〕 HPCと産業クラウドの統合
2.2.5 進化するAI
〔1〕 エージェントAI(Agent AI)
〔2〕 フェデレーテッドAI(Federated AI、連合学習型AI)
〔3〕 フィジカルAI(Physical AI)
2.3 データセンターの最新状況
2.3.1 AIが引き起こした進化
〔1〕 空冷から液冷、液浸
〔2〕 「AI半導体」の開発
〔3〕 量子計算の実用化
〔4〕 C言語の再評価
2.4 これからのAIとのつき合い方
2.4.1 現状のAIの特徴
2.4.2 データの正しい使い方とその意義
2.4.3 フィジカルAIと人間の知覚補完
2.5 AI時代のデータセンター
2.5.1 多様化、分散化するデータデンター
〔1〕 汎用から用途特化型へ
〔2〕 機能に応じた分散配置
2.5.2 ユーザーの変化
〔1〕 計算スピードが競争力に直結する
〔2〕 人手からロボットへ
〔3〕 サプライチェーンのクラウド統合
2.5.3 AIデータ処理の現状
2.6 ワット・ビット連携がもたらす未来
2.6.1 電力系統の変革
〔1〕 「一方向」から「双方向」へ
〔2〕 双方向に対する需要家側の対応
〔3〕 双方向制御におけるデータセンターの新たな位置づけ
〔4〕 ノンファーム型接続
2.6.2 電圧の階層による制約
〔1〕 高圧電力と特別高圧電力の違い
〔2〕 データセンター「2MW」の壁
〔3〕 プライベートAIでの利用
〔4〕 「プレハブ型」「モジュラー型」データセンター
〔5〕 マッチング・プラットフォームによるユーザーの見える化
2.7 データセンターの新たな定義
2.7.1 EVによる移動型データセンター
〔1〕 電力量の試算
〔2〕 計算能力の試算
2.7.2 スケルトン・インフィル型の適用
2.7.3 デジタル地政学の確立による海外投資促進
2.7.4 エネルギー安全保障の変化
2.7.5 国家安全保障におけるAIの重要性
2.7.6 地上から宇宙へ、インフラの最終進化
3.1 これまでのデータセンター立地施策
3.1.1 2021年から議論が始まったデジタルインフラ立地の在り方
3.1.2 【第1期】2022年1月27日公表「中間取りまとめ1.0」
3.1.3 【第2期】2023年5月30日公表「中間取りまとめ2.0」
3.1.4 【第3期】2024年10月4日公表「中間取りまとめ3.0」
3.1.5 政策実行に向けた支援措置と最新動向:総務省と経済産業省の施策
3.2 GX政策と「ワット・ビット連携」
3.3 デジタル行財政改革会議と地方創生2.0
3.4 ワット・ビット連携官民懇談会の設置
3.5 ワット・ビット連携官民懇談会で提示された現状と課題
3.5.1 生成AIの社会的インパクト
3.5.2 地域経済とデータセンター整備の相乗効果
3.5.3 災害リスクへの対応
3.5.4 エネルギー政策との連携強化
3.5.5 電力系統インフラの需給状況とデータセンター立地
3.6 「ワット・ビット連携官民懇談会取りまとめ1.0」の内容
3.6.1 短期:足元のデータセンター需要への対応
〔1〕 既存電力インフラの最大限活用に向けた検討
〔2〕 オール光ネットワーク(APN)による立地の拡大
3.6.2 中長期:データセンターの立地戦略とインフラ整備
3.6.3 長期:技術革新・運用の高度化によるワット・ビット連携
3.6.4 横断的課題【1】:地域との共生、環境への配慮
3.6.5 横断的課題【2】:国際的視点
3.7 今後の展開
4.1 ICT機器の技術方向性
4.1.1 チップはムーアの第2法則へ
4.1.2 チップレット技術の高性能化に伴う消費電力・発熱量の増大
4.1.3 単体サーバからRack Scale Architectureへ
4.1.4 Rack Scale Architecture製品の登場
4.2 ネットワーク機器の技術の方向性
4.2.1 クラウド基盤連続動作実現のためのマルチAZ
4.2.2 大容量ネットワーク(高スループット)と低レイテンシー
4.2.3 「光は遅い」
4.2.4 光ケーブルやCuケーブルは徹底的に短く!
4.3 冷却技術の方向性
4.3.1 空冷の限界
4.3.2 DLC(Direct Liquid Cooling)とASHRAEのWクラス、Sクラス
4.3.3 ハイブリッド冷却(DLC液冷と空冷の併用)と液冷/空冷の割合(Cooling Mix)
4.4 給電技術の方向性
4.4.1 ラック当たり電力の増大と給電
4.4.2 キャンパス型データセンターの給電方法
4.4.3 マレーシアのデータセンターパーク内給電
4.5 電力グリッドオーケストレーション
4.5.1 電力グリッドオーケストレーションの現状と方向性
4.5.2 データセンターの下げDR対応が現実的に
4.5.3 電力グリッドオーケストレーション用ネットワークのセキュリティ
4.6 電力の地産地消
4.6.1 米国の地域電力問題
4.6.2 発電所併設型データセンターと事例
4.6.3 マルチAZを形成するデータセンターのメリット
4.6.4 キャンパス型データセンターと事例
4.7 データセンター容量と熱源設置面積の増加
4.8 熱源問題の考察
4.9 ワークロードシフト
4.9.1 Googleのデータセンター
4.9.2 マイクロサービス化による遠距離データセンター間のワークロードシフト
4.10 ワット・ビット連携の立地選定時に求められるICT機器・ファシリティ技術面からの要件
4.10.1 電力コスト
4.10.2 電力グリッドオーケストレーション
4.10.3 キャンパス型データセンター
4.10.4 データセンターのコンセプト(対象アプリケーション)
4.10.5 ネットワークコネクティビティ
4.10.6 熱源
4.10.7 オペレータのスキルレベル、教育
4.10.8 設備、ICT機器の保守体制
4.11 短期対策、中期対策、長期対策
5.1 データセンター冷却技術の現状と課題
5.1.1 廃熱処理の市場規模が急激に拡大
5.1.2 サーバラックの高密度化による熱排出量の急増
5.2 現在のサーバ冷却システム事例
5.2.1 Microsoft Azureの「リアドア冷却」
5.2.2 産業技術総合研究所(産総研)の「ホットウォータークーリング」
5.2.3 「高温で冷やす」という発想転換
5.3 ハイパースケーラーの採用で注目される「ハイブリッドシステム」
5.3.1 大容量空冷チラー×高発熱対応水冷空調機(AHU)
5.3.2 ラックあたり60?70kVA級の超高密度サーバにも対応
5.3.3 ホットウォータークーリングによって、PUE1.1を実現
5.4 ハイブリッド冷却システムの主要メーカーと製品
5.4.1 「ハイブリッドクーラー市場」の成立
5.4.2 桑名金属工業株式会社(本社:三重県)「チルドタワー」
5.4.3 ニデック株式会社(本社:京都府)「DLCシステム」
5.4.4 Staubli International AG(本社:スイス)「クイックコネクタ」
5.5 ハイブリッド冷却システムがもたらす経済性
5.5.1 冷水温とPUEの関係性を産総研が実証
5.5.2 ハイブリッド冷却システムによって電力コストを劇的に削減
5.5.3 ドライクーラーが冷却効率の向上と水資源の節約にも寄与
5.6 技術の標準化と将来対応
5.6.1 ハイブリッド冷却システムは13?40℃の幅広い温度帯に対応
5.6.2 高発熱サーバにはDLC
5.6.3 供給水温度の調節も容易、柔軟な運用が可能に
5.7 今後の動向
5.7.1 ニデックのAIデータセンター向け「In-Row型CDU」
5.7.2 株式会社バーテック(本社:大阪府)の「BPユニット」
5.7.3 ソフトバンク株式会社の「大規模AI基盤」
6.1 【ハイレゾ】地域資源+AIを利用したGPU特化型データセンターで脱炭素と地方創生を推進
6.1.1 株式会社ハイレゾのプロフィール
6.1.2 志賀町第一、第二データセンター
〔1〕 完全外気導入型
〔2〕 ティアフリー
〔3〕 高圧電力
〔4〕 再エネ活用、下げDR
〔5〕 地方創生、地元連携
6.1.3 香川県に設立された高松市データセンター
〔1〕 既存の企業入居施設「RISTかがわ」をリノベーション
〔2〕 高松市データセンターの主な特徴
〔3〕 既存建物の再利用型データセンター特有の制約
6.1.4 佐賀県の玄海町データセンター
〔1〕 過疎地域の廃校をリノベーション
〔2〕 玄海町データセンターの主な特徴
6.1.5 香川県の綾上データセンター
6.1.6 ワット・ビット連携との共通項
6.2 【Quantum Mesh】液浸冷却技術「KAMUI」(カムイ)を中核とした分散型エッジデータセンターで社会基盤を整備
6.2.1 Quantum Meshのプロフィールと事業ビジョン
〔1〕 Quantum Mesh(クォンタムメッシュ)設立の目的
〔2〕 AI時代における「第三のインフラ圏」の創出を目指す
〔3〕 Quantum Meshのビジョン:GXとGXを同時に実現
6.2.2 Quantum Meshの技術基盤とインフラ構造
〔1〕 中核は独自開発の液浸冷却技術「KAMUI」(カムイ)
〔2〕 「KAMUI」の液浸冷却の仕組み
〔3〕 PUE1.03を達成した「KAMUI」
〔4〕 液浸用オイルの課題とその改善策
6.2.3 コンテナ型データセンター「EDGE HIVE」(エッジ・ハイヴ)
〔1〕 短期間で稼働できるモジュール設計
〔2〕 再エネとの親和性も高い
〔3〕 セキュリティの優位性が大きい
6.2.4 Quantum Meshの事業モデルと投資促進の仕組み
〔1〕 事業モデルの中核:分散型インフラの整備
〔2〕 地域振興と一体となった「社会実装型インフラ」
〔3〕 「データセンター+再エネ」は新たな投資アセット
〔4〕 四層構造がワット・ビット連携の推進力
6.2.5 導入事例と成果
〔1〕 福井県高浜町で稼働したフル液浸ラック型データセンター「高浜ドリップ1」
〔2〕 VENA Energyとの提携:「データセンター+再エネ」をパッケージ
〔3〕 地方自治体や民間企業との協働による応用事例の拡大
〔4〕 地域完結型のレジリエンスの実現
6.2.6 社会的・経済的インパクト
〔1〕 「再エネの主力電源化」と「生成AIによる膨大なデータ処理の拡大」に対応
〔2〕 地方創生の観点からの効果
〔3〕 情報安全保障(情報セキュリティ):情報(データ)主権を守る
〔4〕 「第三のインフラ圏」へのチャレンジ
6.2.7 今後の展望
〔1〕 液浸冷却技術「KAMUI」の短期的・中期的・長期的な展開
〔2〕 「AI・データセンター・半導体」という三位一体による挑戦
6.3 【みちびき】新開発の「モジュール型データセンター」で地方に新たな市場創生を目指す
6.3.1 みちびき株式会社のプロフィール
6.3.2 「みちびき」が進める3つの主要プロジェクト
〔1〕 次世代型データセンターの開発
〔2〕 既存ビルのスマート化
〔3〕 ビルOS、BMSの普及促進
6.3.3 低コストな新型「モジュール型データセンター」の開発
6.3.4 データセンター建設における課題と現状分析
〔1〕 過大な初期投資負担
〔2〕 運用開始までの長期リードタイム
〔3〕 データセンターの巨大化
〔4〕 建設・設計業界における人材不足
6.3.5 モジュール型データセンターとは
6.3.6 モジュール型データセンターがもたらすメリット
〔1〕 建設コストの削減
〔2〕 短期間で稼働開始が可能
〔3〕 多様な立地に開設可能
〔4〕 景観と調和する外観
6.3.7 モジュール型データセンターとコンテナ型データセンターの比較
6.3.8 モジュール型データセンターの主な課題
〔1〕 電力会社の制度整備
〔2〕 民間による市場形成と投資促進
6.3.9 データセンタービジネスの現状分析とモジュール型データセンターの価値
〔1〕 データセンタービジネスの現状分析
〔2〕 ワット・ビット連携時代におけるモジュール型データセンターへの価値
6.3.10 社会的意義とモジュール型データセンター事業の展望
〔1〕 モジュール型データセンター間のネットワーク化によりワークロードシフト(WLS)を実現
〔2〕 30カ所程度の拠点整備を目標に
〔3〕 最終的に電力と通信の負荷分散を目指す
〔4〕 グローバル市場への展開
6.4 【アジャイルエナジーX】ビットコイン・マイニング×DERで「未利用エネルギーの価値化」「地域創生への貢献」を目指す
6.4.1 アジャイルエナジーXのプロフィール
〔1〕 逆転の発想で世界に先駆ける事業を展開
〔2〕 アジャイルエナジーX設立の背景
6.4.2 日本の電力系統が直面する課題
6.4.3 MegaWatt To MegaHashプロジェクト
〔1〕 ビットコイン・マイニングの特徴
〔2〕 アジャイルエナジーXの概念実証(PoC)
〔3〕 アジャイルエナジーXのMW2MH実証サイト例
6.4.4 MW2MHプロジェクトの特筆すべき特長
6.4.5 究極の循環経済構想
6.4.6 世界のビットコイン・マイニング設備の現状
6.4.7 将来展望と「理想的なエネルギー基盤の構築」
〔1〕 未利用エネルギーの価値化
〔2〕 地域創生への貢献
〔3〕 国際連携と日本のイノベーション発信
【コラム】ビットコイン・マイニングとは何か—電力と分散コンピューティングが生み出すデジタルゴールド—
6.5 【DC Power Vil.】直流で「創エネ」「蓄エネ」「省エネ」し高効率に電力を有効利用
6.5.1 DC Power Vil. 株式会社のプロフィール
6.5.2 直流による配電ロス削減と課題
〔1〕 OCPとは
〔2〕 Googleの±400Vdc高電圧直流開発とNVIDIAの800Vdc給電対応MGXラック
〔3〕 60V以上の直流の安全対策
6.5.3 なぜ直流の高電圧が必要なのか
〔1〕 テレコム用のIT機器は48Vdc
〔2〕 配線ロスと直流電圧
6.5.4 直流の課題:いかに安全性を担保するか
〔1〕 感電対策と地絡検出
〔2〕 アーク抑止技術
〔3〕 その他の直流技術
6.5.5 北海道の400Vdc直流データセンター「石狩データセンター」
〔1〕 HVDC 12V方式の高電圧給電で電力効率90%超を実現
〔2〕 太陽光発電の電力を直流のまま送電・給電
6.5.6 直流ハウスと糸島サイエンス・ヴィレッジ構想
〔1〕 世田谷直流ハウス
〔2〕 糸島サイエンス・ヴィレッジ
6.5.7 気づいたら、ほとんどが直流!
〔1〕 使用機器類へ高まる電気容量増大の欲求
〔2〕 時代の転換点:直流システムの経済効果
6.5.8 ワット・ビット連携こそ直流の出番!
〔1〕 直流マイクグリッドで電力を自己消費
〔2〕 直流の分散コンピューティングでエネルギー自給率を向上
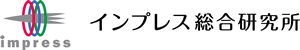
 シェア
シェア ツイート
ツイート